-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年4月 日 月 火 水 木 金 土 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
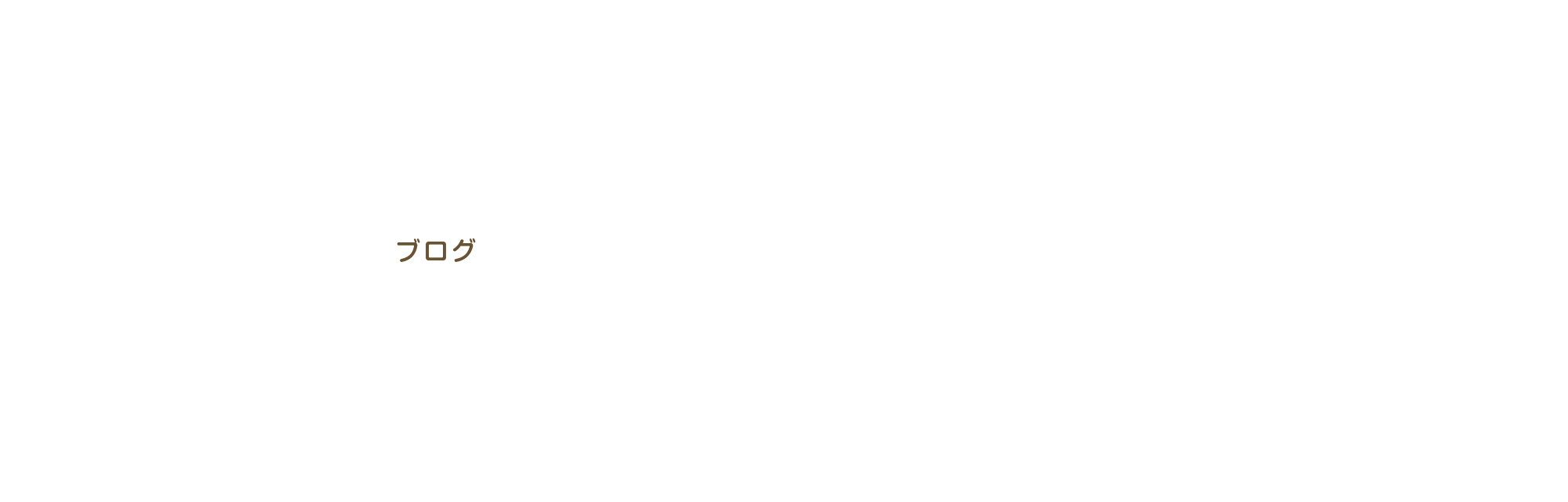
病気の原因のほとんどが、
ストレスにあると言われていますが、
このストレスの軽減に有効とされているのが、
セロトニンという脳内の神経伝達物質です。
セロトニンは、心の働きやバランスのコントロールに大きく関与しており、
セロトニンが活性化すると朝の目覚めが良くなり、
心身共に健康な状態となります。
逆に不足すると不安感が増し思考がネガティブになり、
うつ病や自閉症、その他多くの病気を引き起こすと言われています。
セロトニンは幸せホルモンとも呼ばれて、
これが脳に十分にあれば、うつ病に成りにくいとされていて、
実際に一般的なうつ病の投薬治療は、
脳内のセロトニンを増加させる薬が使われているそうです。
では、うつ病は心の病?では無くて
、脳内の問題なのでしょうか?
続きは、また次回。
祈りと感謝は、いつもワンセットです。
「いただきます。」と
「ごちそうさま。」の様に。
どちらも何気ない日常のありふれた
挨拶の言葉のようですが、
国によっては、食事の際に宗教的な儀式は行なわれても,
「いただきます。」「ごちそうさま。」のような挨拶をしない所もあります。
言葉は、その国に暮らす人々の考え方や、
生活、文化が色濃く
反映されています。
人間の身体は、その人が生きて食べて来たもので出来ていて、
そして、その人の思いによって、動いています。
そういう意味では、
何を食べるかは、勿論大切ですが、
どういう思いで食べるのか…は、
もっと大切と言えます。
「命を大切にする。」
「感謝して頂く。」
何気ない挨拶の言葉に込められた意味に思いを馳せる事は、
食べる事の意味=自分自身の生きる意味や、
命を大切にする事につながるのでは無いでしょうか。
挨拶は大切に、心を込めて。
私達は、日頃生活する上で多くの人達の親切や、
社会的な恩恵を受けています。
ご飯を作って貰ったりだとか、
電車で席を譲って貰ったりだとか。
目に見える形で受けた心遣いには、
有難いと感じ、言葉にすることが出来るのですが、
ほとんどの場合は、気付かれる事無く、そこに存在しています。
例えば、お日様だったり、身体の免疫機能だったり、
亡くなったおじいちゃんの思いだったり…。
目に見えない事を解る為には、
どうしたらいいのでしょうか?
それは、感じるしか有りません。
感じる為には、ある程度の感受性と想像力が必要です。
今まで知らなかった、考えてもみなかったし、気にも留めて無かった。
けど心静かに感じてみると
本当はずっと守られていたんだ。
ずっと愛されていたんだ。
今まで気も付かずにお礼さえ言ったことも無かったなぁ。
本当に申し訳無かった…。
そんな風に「感じて謝る事」。
それが、感謝の心です。
そして、それを「気づき」と言います。
気(エネルギー)つき(ラッキー)
「気づき」は、幸せへと導いてくれます。
今は、受験シーズン真っ盛り。
志望校を目指して、寝る間も惜しんでの勉学の日々。
でも、やっぱり
最後は神頼み。
天神さんに「合格祈願」の絵馬を奉納します。
「祈願」いわゆるお願いをするわけです。
これに対して純然たる「祈り」は、
お願いではありません。
「祈り」は「意宣り(いのり)」と書き、
自分の意(こころ)を宣る(宣言する)と言う事を表します。
つまり、私はこうします。
こういう生き方をします。
と神に誓うのです。
私は医学部に入って、沢山の人の役に立ちます。
どうか見守って下さい。
そして導いて下さい。
と言うのがいわゆる「祈り」です。
お願いしちゃいけないと言う訳では、有りません。
でも、結果の有無に関わらず、
お願いには其れなりの対価(お礼)が必要ですよね。
「ごちそうさん」
NHK大阪放送局の朝の人気ドラマです。
大阪人は、家の食事だけで無く
外食のあとでも、店員さんに
「ごちそうさん。美味しかったで。また、来るわ。」
と声をかけます。
「ごちそうさま」
漢字で書くと「御馳走様」
昔は、今と違い食材を調達するのも大変な事でした。
「馳走」とは、
駆けずり廻って、奔走するさまを表しています。
大変な思いをして、食材を集め、料理を作って下さった方に
感謝の意を込めて、丁寧語の
「御」と「様」が付いて
「御馳走様」
「いただきます」が、
あなたの命をわたしの命とします。
と言う意宣り(いのり)の言葉。
そして「ごちそうさま」は、
その命を、料理(いのちの糧)に
変えて下さった方への感謝の言葉。
どちらも美しい日本人の心です。
日本の気候は、
大陸ほど極端な気温の変化が少なくて、
(最近はちょっと変ですが)
四季の移り変わりがある為にゆるやかに穏やかに流れて行きます。
その為に、日本人はあまり強い刺激を好まず、
比較的、繊細な感覚の方が多い様に見えます。
それに合わせて鍼もより細くてしなやかになって行き、
鍼先は松葉形と呼ばれる進入し易く、
また痛みを感じにくい形のものへと、
進化して行きました。
また、飲み薬も、国内に生育している植物由来のものがほとんどで
(中国では、鉱物や動物由来のものも多いです。)
身体に優しく、効き目も比較的穏やかになっています。
中国の漢方薬に対して、日本のそれは、
日本式の漢方薬=「和漢薬」と呼ばれる事もあります。
*三回に分けて、日中韓それぞれの違いを書いてきましたが、
ある一面をかい摘んで記したもので、決して全てを表したものでは有りません。
参考程度にお読み頂ければ幸いです。
気候、風土や生活習慣、
食べ物といったものが変われば
そこに住む人々の体質にも影響を及ぼします。
それに合わせて、治療方法も少しづつ変化して行きます。
同じ中国の国内でも寒い地方と暖かい地方では、
当然違います。
昨日のブログの内容は、
王先生の勤務されていた上海の病院では…。
という事になります。
韓国の場合、一番の特徴は、
肘から先、膝から先、
或いは顔や耳といった服を脱ぐこと無く
既に露出している部分のツボで
全身の調整を行なう事が多い
という事です。
ご存じの通り、ツボというのは
全身にくまなく分布している訳ですが。
寒さの影響もあると思いますが、
何と言っても儒教の教えによるところが
一番大きいと思われます。
特に女性の場合などは、
治療であっても人前で肌をさらす事に
抵抗を感じる方が多い様です。
それに伴って、
発展して行った治療方法と言えるかもしれません。
韓国における儒教の影響は、
我々の想像以上に強く残っていて、
治療現場でも日本の場合より、
より伝統的、東洋的な感覚が強く、
初めて治療を受けた時などは
少し戸惑いを感じる事が有るかもしれません。
JR芦屋駅から徒歩2分
杏林堂鍼灸整骨院の院長ブログです。
家族と共に来日されていた王先生は、
日本の大学に入学された娘さんの卒業を待って帰国され、
上海の大学に復職し、また以前の様にご活躍されているそうです。
王先生から伺った話では
中国の場合、
西洋医学のお医者さんを西医、
伝統的な療法を行うお医者さんを中医と言い、
それぞれに認められた存在で、
患者さんはどちらかの治療法を選ぶ事が出来るそうです。
もちろん、併用する事も可能です。
症状によって、この場合は西医にこちらは、中医に。
また、西医に見て貰いながら漢方薬も処方して貰う。
と言う具合です。
非常に合理的ですね。
ただ、お国柄と言うべきか、
何事も大陸的というのか
全てにおおらかで
治療の際には、
先生の前であっても、結構大胆に服を脱いで、
診察台の上に
横たわる方も多いのだそうです。
先生を信頼して、全てをゆだねる…。
という事だと思いますが。
また漢方薬などは、入院中の患者さんに出される場合、
毎朝
一日分として、大きなヤカンでどーんと
持ってこられるそうです。
鍼についてはご存じの通り、いわゆる中国鍼と言うもので、
長いし、太さも結構あります。
体格や、感受性の違いも影響しているのかもしれません。
鍼先の研磨も割とランダムで、
日本人の我々には、ちょっと厳しいかな?
と感じる時も正直あります。
その点、
日本や韓国では?
それは、また次回に。
私たちは、食事をする際に
必ず手を合わせて
「いただきます。」
と言います。
「戴きます。」
あなたの命を頂戴致します。
「頂きます。」
頂き。
即ち、上(かみ)からの賜り物を頂戴致します。
と言う意味合いと、
私たちは、
食物連鎖の頂点、
「頂き。」に居ます。
という事実を食事の度に
再確認する作業
とも言えます。
連綿と続く食物連鎖の輪、
それは、
いのちを受け継いで行く作業。
あなたの全てを受け容れます。
あなたの生きてきた全てを引き受け、そして受け継いて生きます。
食事の度に、
そう宣言しているわけです。
「いただきます。」
美味いや、不味いだの
ましてや、有効成分のみを抽出して…..
(栄養だけを考えて。)
なんて話しとは、まるっきり違います。
ありがたく全てを受け容れる。
一物全体主義。
本来の「医食同源」とは、
こういうところから来ている
のかもしれません。
二つ目の違いは、
お薬に対する考え方、
いわゆる
製薬に対する考え方そのものの違いです。
もっと言えば、医療制度そのものの違い
と言えるかもしれません。
一般的に、患者さんに投薬出来るお薬として認められる為には、
長い間の研究と実証が何よりも肝要です。
何が身体に作用し、有益なものなのかのデータが必要と成る訳です。
つまり、元となる生薬の中にある有効成分のみを抽出したのちに
精製されたものがお薬として認められるのです。
一方、漢方薬、特に煎じ薬の場合はそうでは有りません。
そもそも
有効成分を抽出して、という考え方そのものが有りません。
そのもの全体が有益であり、
また何が欠けていても駄目で、
何が実際に作用させているのか分からないし、
自然の中には、我々の知らない
いわゆる「雑味」
と言われるものの中にこそ求めるものが隠されているかもしれません。
だから、生薬全体を一つのものとして全て頂く。
という考え方です。
これを一物全体主義(いちもつぜんたいしゅぎ)と言います。
かなり、違いますよね。
料理の場合でも、
えぐ味のもとである灰汁(あく)を丹念に取り除きますが、
もしかしたらその雑味の中にこそ、
身体に良い物が含まれているのかもしれません。
まあ、食事というのは漢方薬と違って
美味しいに越した事は無いのですが…。