-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年4月 日 月 火 水 木 金 土 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
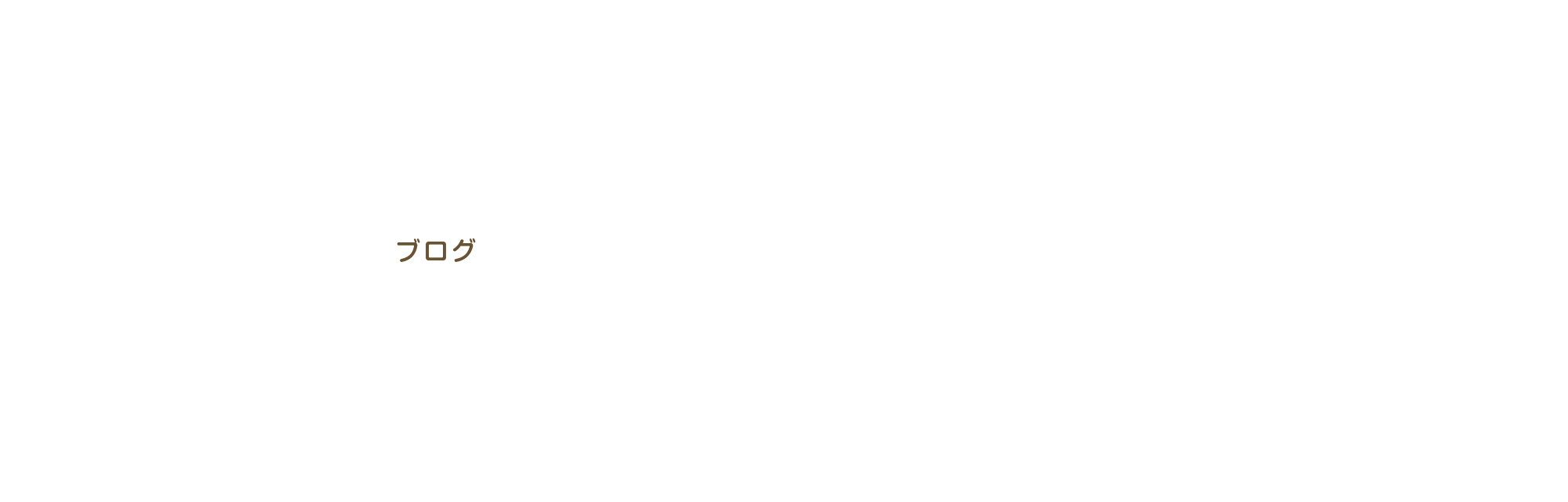
もともと農耕民族であった日本では、
乳を原料にしたヨーグルトのような
酪農乳酸菌系の発酵食品は定着していませんでした。
では、発酵乳文化が伝わる以前の日本人は
どうやって乳酸菌を摂って来たのでしょうか?
ヨーロッパの酪農乳酸菌系に対して、
日本のそれは植物由来の乳酸菌=醸造乳酸菌系と言います。
具体的には、長期醸造した味噌や醤油、たくあん、ぬか漬けや納豆など
いわゆる和食の代名詞とも言える食品群です。
セロトニン関連での不飽和脂肪酸の多い青魚、
食物繊維の多い海藻や野菜、豆類、玄米などと共に、
乳酸菌の多い味噌、醤油、漬け物、納豆など全て合わせて
「THE和食」。
ストレスの多い現代社会。
さらに、夜型の生活で、朝食は抜き、お昼は外食、
夜は
ハンバーグなどの洋食、そして夜食にラーメン。
ますます伝統的な和食を食する機会が少なくなって来ています。
統計的にも、うつ病や自律神経の症状を訴える方の
食生活は乱れている場合が多いと言われています。
腸内環境という観点からも改めて、
日本人には、日本人の…。和食を見直してみては如何でしょうか?
私たち日本人は、牛乳を飲んだらお腹をこわしたり、
乳製品でアレルギー症状がでる割合が
比較的多いかもしれません。
個人差は有りますが
、乳製品に長く親しんで来た民族に比べて
消化、吸収する能力が弱いと言えます。
では、日本人は乳製品を摂っても意味が無いのでしょうか?
決してそういう訳では有りません。
長い歴史のある民族と全く同じとは言えない。
というだけです。
ただ、明治以降にヨーロッパから伝わった
発酵乳の文化ですが、
今では日本は世界トップレベルの乳酸菌王国と言えます。
1917(大正6)年にビオフェルミンが誕生。
1919(大正8)年にカルピスが、
1935(昭和10)年にはヤクルトが発売され、
その後も数多くのメードインジャパンの発酵乳製品が
世に送りだされています。
今ではさらに進化したナノ型乳酸菌が誕生し、
日本人の腸にも効率良く
消化、吸収出来る様になって来ています。
*メディカル出版研究所
「腸内解体新書」 参照
前回の健ちゃんと康子さんの会話、どう思われましたか?
我々、哺乳類はおっぱいを飲んで大きくなります。
でも、それは赤ちゃんの間だけで、
長ずればそれぞれにカラダに合った食物を口にします。
それは、どの種も同じです。
そう、おっぱいは赤ちゃんの身体を作る為にのみ必要な成分なのです。
そして、それはその種ごとに特有のもので、
牛のおっぱいは牛の赤ちゃんの身体にとってのみ必要な栄養分なのです。
人間は、人間の。クジラはクジラの…。
人間のように他の種のおっぱいを口にしている動物は居ません。
人間は、生きて行く為に長い歴史の中で他の種の乳を消化し、
吸収して栄養分とする仕組みを
自分の身体の中で作り上げて行ったのです。
DNAに組み込んでいったと言っても良いと思います。
しかし、農耕民族である日本では
乳を原料にしたヨーグルトのような
酪農乳酸菌系の発酵食品は定着していませんでした。
DNAに取り込まれるという行為は、
何年間摂り続けたから、獲得するというものでは無く、
何世代も掛けて
というレベルのものなのです。
では、農耕民族である我々日本人にとって
乳製品は有益なものでは無いのでしょうか?
これは、何にでも「どうして?」と疑問に思ってしまう
ある男の子(健ちゃん)とお母さん(康子さん)の会話です。
気楽に読んでみて下さい。
「健ちゃん、ちゃんとヨーグルト食べてる?」
「まだだけど、どうしてヨーグルト食べなきゃいけないの?」
「それは、お腹に良いからよ。」
「そうなんだ。でもヨーグルトって何で出来てるの?」
「それはね、牛さんのおっぱいから作られてるのよ。」
「ええ!牛さんのおっぱい?
じゃあ、僕は牛さんの赤ちゃんなの?」
「何を馬鹿な事を言っているの。健ちゃんは人間の子供に決まってるでしょ。」
「でも、どうして人間なのに牛さんのおっぱい飲むの?それに
おっぱいって赤ちゃんのものでしょ?僕、もう幼稚園に行ってるよ。」
「あのね、健ちゃん。昔から、
ブルガリアヨーグルトって言ってヨーロッパなんかの色んな国の大人の人達が
ずっーと飲んでてみーんな長生きしてる良いものなのよ。」
「ええー。じゃあ、お父さんかお母さんか、ブルガリア人なの?」
「健ちゃん、笑わせないでよ。そんなはず無いでしょう。二人共、れっきとした日本人よ。」
「じゃあ、どうして日本人なのに…、」
「健ちゃん、怒るわよ。
あのね、何人とか関係無いの。
みんな同じ人間なの。身体に良いものは、みんな良いのよ。
分かった?分かったら早く食べてしまいなさい。」
TVを点けるとちょうど、うつ病とセロトニンの関係を
ある大学の先生が説明していました。
そのお医者さんの話では、うつ病の方は朝、
太陽の光を浴びて散歩するのが良い。との事でした。
太陽の光には、セロトニンの分泌を促す作用があると言われています。
また、散歩などの有酸素運動にも同様の作用が期待されているからです。
でもまあ、引き籠っている患者さんが、
自ら早起きをして朝の光り輝く陽光の中を散歩出来るように為っていれば、
かなり快復に向かっていると言えるのでは、ないでしょうか。
食事についても言及されていて、
お魚類、特にイワシやサバなどの青魚に含まれる
不飽和脂肪酸やDHAが良いとの事でした。
それとは別に、腸内環境を整える為には、
食物繊維と乳酸菌が有効と言えます。
食物繊維は、悪玉菌によって生み出される腐敗物質を
便と一緒に押し出す事で、結果的に腸内環境を改善してくれます。
豆類、野菜、海藻類、また玄米なんかにも特に多く含まれています。
そして、善玉菌の代表であるビフィズス菌や乳酸菌ですが、
乳酸菌=ヨーグルトのような乳製品と言うのが、
一般的なイメージになっていますが、果たしてそれは…。
また、次回。
昔からよく、病は気から
と言いますが、
現代社会に於いてはそのほとんどが、
ストレスに起因しているとも言えます。
ストレスの要因も多種多様で、
ライフスタイルの変化に伴う夜型生活への移行や、運動不足、
パソコン、スマホ等の電磁波の影響、化学物質や大気汚染など
以前では考えられ無かったものの影響も無視する事は、出来ません。
もちろん、仕事や健康上の悩み、人間関係のトラブルなど
数え上げればキリが有りません。
また、食事を見直す事だけで現実に存在するストレスが
すべて消えて無くなると言っている訳では有りません。
上司がイヤミをいわなくなったりとか、
子供の成績が突然上がったりとか…。
腸の状態を整える事によって、
ストレスが軽減したり、ストレスに強くなる
神経伝達物質が分泌されやすくなり、
ひいては病気に対する抵抗力が増して、罹りにくくなります。
と言う訳です。
その片はお間違え無い様に…。
何を食べるかについては、次こそ。
二月の中頃から、三月の中旬過ぎ迄のこの時期は、
毎年花粉が到来する(近年は、黄砂やPM2.5も)
何とも困った季節ですが、
また確定申告の時期でもあります。
どちらも頭を悩ましている方が多いと思いますが、
医療費控除の方はもうお済みでしょうか?
毎年、どこまでが認められるのか悩まれている事と思います。
風邪の治療の為に薬店で買った市販の風邪薬はOKで、
お医者さんで打って貰ったインフルエンザの予防接種は認められ無い
と言われると、何が何だか分からなく成ります。
簡単に説明すれば、実際に病気や怪我をして、
それを治す為に掛かった費用は、OKです。
実際には、罹患していないけれど、
罹らない様に予防したり、
対策を講じたものは、認められませんよ。
という訳です。
花粉症などの鼻炎の為のお薬はOKですが、
予防の為のマスク代や
花粉が服に着きにくくするスプレーとか、
部屋の空気清浄器なんかは、駄目でしょうね。
目をカバーする眼鏡なんかもそうでしょうし、
ぜんそくを改善させる為に、体力をつけようと思ってプールに通ってます。
なんていう費用は、認められ無いでしょう。
医療費として認められないと言うことは、
つまり予防法は医療の範疇に含まれていない。
と言うことを表しいると言えます。
一方、東洋医学では、「未病」と言う考え方があり、
症状が現れる前に治療する。
病気に罹りにくい体質に改善して行く。
と言うことが、実際に症状が現れてから治療することよりも重要である。
と考えられています。
未病の考え方や、実際の体質改善法については、
また日を改めて少しづつお話していきたいと思います。
杏林堂鍼灸整骨院のある芦屋市は、
南北に長く、東西が狭いいわゆる縦長のかたちになっています。
北を見れば六甲山系、南に向かえば、瀬戸内の海。
自然に恵まれた本当に静かな住宅街です。
JR芦屋駅から続くアーケード沿いの商店街にある
私たちの治療所からも、お天気の良い日は、
入り口側のガラス窓を通して六甲の山々を望むことが出来ます。
でも、この二、三日はお天気は良いのに空は白っぽく、
山はかすんで見えます。
暖かくなって来たので、春霞かな?と思いきや、
そうでは有りません。
中国からやって来たPM2.5の仕業です。
そう言えば、朝から患者さんも
咳込んだり、鼻水がツーと流れたりする方が多かった様に思います。
兵庫県にも、注意喚起が出された様で、
テレビでは外出を控える旨の報道がありました。
私も、夕方過ぎると何と無く、頭が痛い感じがします。
もともと、鼻炎やアレルギーのある方はもちろんの事、
身体の丈夫な方にとっても、これはたまりません。
今まであまり実感が無かったのですが、やはりこれからは
マスクは必要なものだと思います。
体調の勝れない方は、
場合によっては、外に出ない方が良いのかもしれません。
悪くなれば治療をする。
また症状が出ない様に体力をつけたり、
場合によっては体質を改善したり、
という事ももちろん大切な考え方なのですが、
それよりも先ず、自己防衛をする、予防法を考える。
と言うことが
何より重要な事だと思います。
では、実際の治療現場(国としての立場)では
どう考えられているのでしょうか?
腸の働きは、食べた物を消化、
吸収して便を作るだけでは、ありません。
排便の支配は脳から受けますが、
それ以外の動きは腸が独自に行なっています。
また、さまざまなホルモンが分泌され、
第二の脳と呼ばれるくらい多様な働きを持ちます。
食べた物を消化、吸収して栄養分を全身に供給する腸は、
いわば「健康の源」と言えます。
身体に良いものを摂れば、健康に。
反対に身体に有害なものを吸収してしまったら…。
腸は、「病気の源」となってしまいます。
東洋医学では、その人の親から受け継いだ、
いわゆる持って生まれた元気の素を「先天の精」と言い、
「腎」(腎臓そのものでは有りません。)に宿る、とされています。
それに対して、生まれてから獲得する元気の素を
「後天の精」と言い、食べ物から補う。
とされています。
つまり、生まれた時には、虚弱であっても、
良い食事を続けていれば、健康になる。
逆に、生まれつき頑健な身体であっても、
悪い食事を続けていれば、病気になってしまう。
と言う訳です。
それほどに、食事は大切だと言う事を表しています。
では、何を食べれば(何が腸に)
良いのでしょうか?
それは、また次回に。
JR芦屋駅北口徒歩二分
杏林堂鍼灸整骨院の院長ブログです。
前回の続きです。
脳の治療を行なえば、
うつ病は完治するのでしょうか?
お薬で脳内のセロトニンを増加させただけで治るほど、
うつ病は単純な病では無いようで、
時に副作用を引き起こす場合もあるそうです。
これには、理由があって実は、
セロトニンの95%は腸のぜん動運動とともに分泌されていて,
肝心の脳内での分泌は、わずか3%程度のみ。なのだそうです。
脳内の問題よりも、腸内環境が大きく係わっていると言えます。
つまり、
腸がしっかりとぜん動運動する
→セロトニンが分泌される
→ストレスが軽減され、心が安定する。
という図式が成り立ちます。
よく「腸=第二の脳」と言われる所以がこれです。
またまた、続く。