-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年4月 日 月 火 水 木 金 土 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
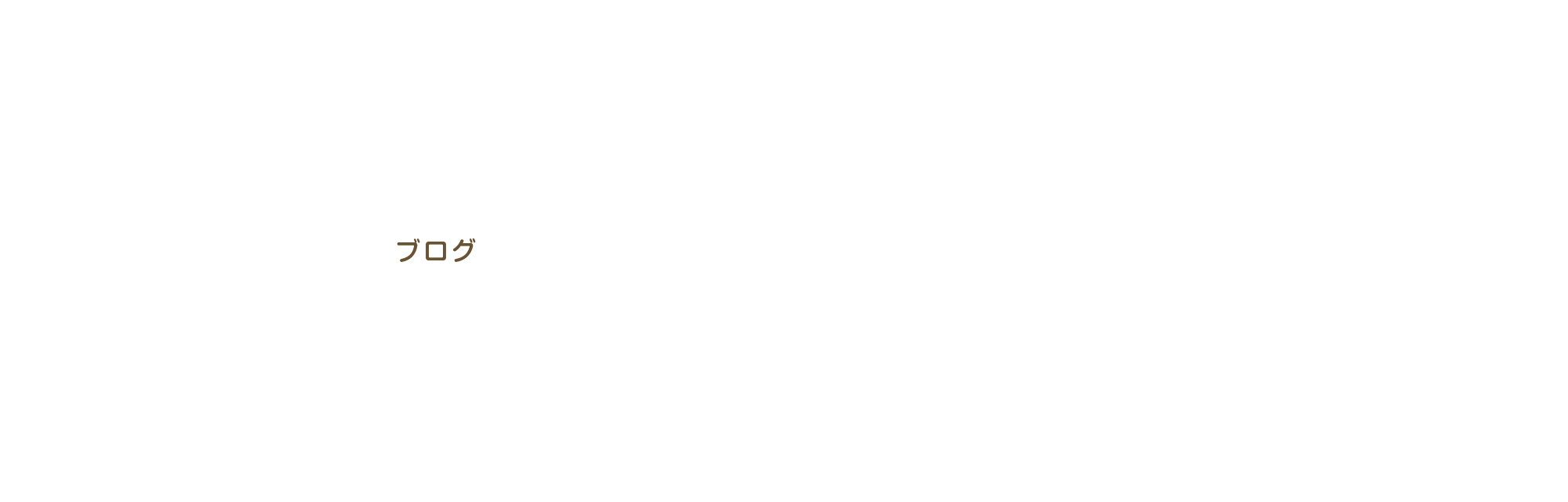
気圧が低下すると、血管が拡張する。だけではありません。
これに加えてヒスタミンという体内物質の分泌による追い打ちがあります。
ヒスタミンは外部からの刺激があると肥満細胞から分泌され、
免疫活動に指令を出す働きをします。
しかし、この働きも過剰になれば、
いわゆるアレルギー症状の原因となります。
最近の研究結果で、気圧とヒスタミンの分泌の関連性が
ある程度、解明されてきました。
それは、人間は低気圧に晒されると
ヒスタミンの分泌が増加するというものです。
低気圧時には、副交感神経の過剰な働きに加えて
ヒスタミンの過剰な作用も合間って「体調不良」がひどくなります。
・免疫の過剰反応→アレルギー症状
(鼻水、くしゃみ、痒み、喉の腫れ等。)
・血管浸透性が増す。
血管から水分が滲み出る。→いっそうむくみが強くなる。
・血管拡張作用→いっそう血圧が下がる。
といった症状が表れます。
※低気圧によるヒスタミンの分泌促進に付いては、
まだ詳細な仕組みは解明されたわけではありませんが、
急激な気圧の変化を「外部刺激」と捉えているのでは…
と考えられています。
気圧が低下すると、身体がだるくなったり、
眠たくなったりすることがあります。
と、前回のブログで書きましたが、
症状としては、それだけではありません。
気圧の変化というものは、身体に物理的な影響を及ぼします。
「隣合った物質は、お互いに干渉し合い平均化しようとする。」という法則があり、
一般的に圧力が高い方から、低い方へと流れようとする性質があります。
人間の身体は、「水の袋」に例えられるように2/3が水分で出来ています。
その体内の水分が、圧力が低くなっている空気中に向かおうとし始めます。
そして、細胞内の水分も外へ、外へと膨張します。
その為に、
・血管が拡張する→血圧が低下する。
・むくみ易くなる。
そして、頭部の血管が膨張すれば、頭痛の原因になります。
その他、まぶたが腫れぼったい、下肢が浮腫む。
また喉の血管が膨張すれば、気道が腫れて喘息の発作を誘発します。
そして、低気圧の時は雨降りなどで、湿度も上がっている為に、
汗をかいても十分に蒸発できずに、
余分な水分が身体に留まり、いっそうむくみの原因となります。
以上、血管拡張に関するお話でした。
次回は、低気圧とアレルギー症状について…です。
気圧と自律神経の関係は、
・お天気の良い日→高気圧=空気中の酸素濃度が高い
→活動モードに→交感神経が優位に働く。
・お天気の悪い日→低気圧=空気中の酸素濃度が低い
→お休みモードに→副交感神経が優位に働く。
もの凄く大雑把に説明すると、こんな感じになります。
そして、私たちは様々なセンサーを駆使して、
この気圧の変化を感知します。
・呼吸から「酸素濃度が薄い。」
・目から「光が少ない。(暗い)」
・内耳にかかる圧力の変化から「気圧が低下した。」
その結果、脳が「今は、活動には適さない環境だ。」と判断し、
副交感神経優位の指令を出します。
副交感神経優位になると、
身体は「休息とエネルギー蓄積モード」に切り替って行きます。
・血圧、血糖、心拍の低下。
・疲労感が増し、意欲低下。
・分泌、排泄機能の低下。
・食欲増加、消化吸収促進。
・心身のリラックス
「外は暗いし、空気は薄いし、今は無理に動かずにじっとしてた方が良いよ。」
的な、感じになります。
その為、低気圧になると、
だるい、眠い、疲れる。という症状が出やすくなる訳です。
何も「低気圧」が問題なわけでは無く、
急激な気圧の低下、またはその最中が症状を引き起こす原因になります。
台風接近時のように急激に気圧が低下すると、
自律神経の行き過ぎた調整が行われて、
それが身体の不調に繋がるという訳です。
続く。
お天気が悪くなると、体調がすぐれなくなる。
または、症状の変化が天候と密接に結びついている病状のことを
「気象病」と呼びます。
雨が降れば古傷が痛んだり、頭痛や耳鳴りがしたり。
「膝の具合で、天気予報が出来ます。」何て言う方もおられます。
同じお天気絡みでも、「私が、旅行に行くと必ず、土砂降りです。」
と言うのは、また別です。
こちらの「雨男、雨女」の方の原因は、不明ですが
「気象病」は、ほとんどが自律神経の状態に起因していると言えます。
自律神経の役目の一つに、
外部環境の変化に身体を適応させるという仕事があります。
お天気による体調の変化とは、
天候という「外部環境」に対応しようとする自律神経が
、ちょうど良い加減なところをさぐって逡巡している状態と言えます。
気象の変化を具体的に挙げれば
・気温の変化
・気圧の変化
・湿度の変化
になります。
そして今回の様な、大型台風の場合は、
「急激な気圧の変化」がもっとも大きな要因と言えます。
台風の接近に伴い、頭痛がしたり、身体の節々が痛んだり、
だるくなったり、眠たくなったり,
また持病の喘息が悪化したり、
といろいろな症状が表れたりすることがあります。
これは、「930hPa」とか言うような「低気圧」が
自律神経に何らかの影響を及ぼして引き起こされる…と考えられています。
低気圧が症状を引き起こす機序と、その対策に付いては、
また次回に。
「梅雨」と言えば、連日シトシトと雨が降り続いて、
洗濯物も乾かないジメジメとした鬱陶しいイメージでしたが、
近年ではその様相もガラッと様変わりしているようです。
以前なら梅雨の晴れ間は、本当に貴重なものでしたが、
今年の阪神間、特に神戸〜芦屋辺りでは、
逆に雨が降って無い日の方が多いくらいで、
場所によっては梅雨の時期としては、
数十年ぶりに少ない降雨という所もありました。
そのせいかどうか分かりませんが、
ここ数年来、芦屋川の上流で観察されるようになった「蛍」たちも、
今年はピークの時期を迎える事無く、
その短い一生を終えてしまいました。
何となく儚い感じがします。
少しばかりの雨が降っても、阪神タイガースの勝利と同じで長続きしません。
交流戦が終わり、このところ珍しく連勝しているので、
何か無ければ良いが、と心配していたら案の定、超大型台風発生の報。
この夏、水不足にならない為にも、雨はある程度降って欲しい処ですが、
強い風や土砂災害だけは何とか避けたいところです。
とは言え、地域によっては、沖縄や九州、そして関東の一部では、
激しい風雨や、雹(ひょう)、それに局地的なゲリラ豪雨などによる
被害の状況をニュースなどで、目にする機会が今年は特に多いように思います。
また新たな災害が発生しない事を心から祈ります。
そこで、と言う訳では有りませんが、遅ればせながら、
これから梅雨〜盛夏に懸けての高温で多湿な時期の過ごし方や、
留意する点、食事や東洋医学的な考え方などを、
数回に分けて書いて行きたいと思います。
今日、7月7日は「七夕さま」です。
一年に一度だけ、彦星と織姫が天の川で出逢うことが出来る日です。
が、何でこんな梅雨どきに設定したんでしょうか?
体育の日前後なら、もっと会える可能性は高いのに…。
何て、お節介はさておき。
私が子供の頃は、夏の初めに夜空を眺めていたら、
結構な確率で「流れ星」を見ることが出来ました。
よく、流れ星に3回願い事を唱えると、その願いが叶う…。と言いますが、
実際そうなった人は居るのでしょうか?
そんな一瞬の間に、3回も。
とても無理、無理。子供心にそう思っていました。
「よく、星に願いを。って言うだろ。
あれはな、何も本当に
「星」がお願い事を叶えてくれるって事じゃないんだよ。
そんな、いつ出て来るか解らないような
流れ星が、突然目の前に現れた時に、
とっさに願い事なんて言えると思うかい?
この流れ星の意味というのはなぁ、
そんな偶然の様なチャンスに、堂々と
「自分はこんな風に成りたいです。こんな事がしたいです。」
って大声で言える、そんな強い意思こそが、
夢の実現へと導くのであって、星が叶えてくれるんじゃ無い。
自分自身の心が叶えさせるんだよ。
何れだけ強い願いか?
流れ星に試されてるって事だよ。
わかったかい。」
これは、もう亡くなった俳優の渥美清さんの言葉です。
映画「男はつらいよ。」の中の台詞…。では無くて、
晩年に付き人を為れていた方に、
日頃何かに付けて、お話しされていたものだそうです。
「星に願いを。」
私たちは誰でも一人一人、
心の中に「希望」や「夢」という名の「星」を輝かせています。
本当の自分の願いとは、何れだけの強さなのか?
見上げてごらん。じゃあ無くて、
見つめてごらん。
「まだ生きてるよー。」
某梅酒メーカーのCMのおじいさんみたいに、
直ぐに反応が有れば分かり易いのですが、
声を掛けても言葉や表情といったサイン(表現)や、
反応が無くて「これは、大丈夫?」となった時、
皆様はどう為れますか?
多分ほとんどの方が、
・脈は、有るか?
・息をしているか?
を先ず、診て、確認されると思います。
この「呼吸」と「脈拍」の2つに
「体温」、「血圧」そして「意識状態」を加えたものを
「バイタルサイン」と呼びます。
バイタルサインは、医療における生体情報、
特に生命維持に必要な「生命兆候」を意味します。
「肉体」を介して、発する「生命」の表現。
今、「生きている。」というサイン。
特に呼吸は「息をしている。」
から、「生きている。」という言葉になった。
と言われるぐらいに、生命(いのち)と直結しています。
息の仕方に、その方の生き方が表れる…。
なんて言い方を為れる先生も、中には居られます。
では、皆さんは今、どんな生き方(息の仕方)をされていますか?
浅いか、深いか?
楽に、息が出来ているのか?
息苦しかったり(生き苦しい)、
息詰まる(行き詰まる)感じがしていないか?
はたまた無理に突っ張って、粋がって(息が上がって)いないか?
そんな時は、ちょっと一息。
肩の力を脱いて、大きく胸襟を開いて先ずは、深呼吸。
そして、横隔膜を動かしてお腹の底から、笑ってみましょう。
何もかも笑い飛ばして、笑顔に成れたら、
まだまだ「脈は有ります。」
後は、一緒に息を合わせて、(息を)調えていきましょう。
おまかせ下さい。
生きている間に、いろんな事を体験する事が、生きる「目的」ならば、
表現することは、「生きることそのもの」と言えます。
どんなに強くなっても、正しく生きても、世の中、色々有ります。
生きていれば、嫌なことに必ず遭遇します。
どんなに精神論を振りかざしても、
目の前から消えて無くなる訳では有りません。
楽しいか、楽しくないか。
だったら、何でも愉しまな。
悩みを笑いに変える。
そんな生まれ乍らのセンスの良さが、関西人には、備わっています。
生きることは、表現すること。
私自身、そう考えています。
ならば、表現する為のツールは多いに越したことは有りません。
人によって表現方法はさまざまです。
人前で、話をする。歌を歌う。ダンスをする。
身体を使って気持ちを伝える。スポーツをする。
とにかく一番を目指す。走る。山登りをする。
写真を撮る。文章を書く。絵を描く。動画を作る。
設計をする。物を作る。
日常生活でも、そうです。
友人とおしゃべりをする。ショッピングをする。
お洒落をする。お化粧をする。習い事を始める。
誰かを好きになる。ドライブをする。旅に出る。
子育てをする。食事を作る。
家族の世話をする。
仕事をして、お金を稼ぐ。事業展開する。
ボランティアをする。
勉強をする。指導する。誰かの役に立つ。
人を笑わせる。etc…。
私自身も、このブログを通して、「心と身体」の健康と言う観点から
何か表現することが、出来れば良いなぁ。と考えています。
しかし、世の中には、楽しい事ばかりでは無く、
中には自分を表現する方法として、
反社会的な行動や、犯罪行為といった
極端な方向に走ってしまう方も残念ながら有ります。
また、愚痴や不満や怒りや悲しみをストレートに表現したり、
逆に表に現すことが出来ずに、溜め込んで、
病気や身体の不調和という形で表現されてしまうケースも実際、
見受けられます。
生きることは、表現すること。
ならば、自分自身も周りも全てが、
「笑顔」に成れる表現方法を心がけたいものです。
そして、私も「施術」という表現で少しでもお役に立てれば…
と日々、研鑽中です。
人は何故、生きるのか?
何の為に生きようとするのか?
有史以来の大命題です。
まあ、そんなに大袈裟に構えなくても、
誰でも一度は考えたことが有るはずです。
人間が「生きる」基準と言うものが、
昔々は、種(しゅ)を残す為、または生き残る為に、
「強いか、弱いか。」「損か、得か。」だったのが、
ただ「生き延びる」だけでは無く、
「より人間らしく」生きる為に、
「善か、悪か。」「正しいか、正しくないか。」が問われる様になり、
そして現代では、より「自分らしく」生きる為に、
「楽しいか、楽しくないか。」が行動する際の判断基準であるべきだ。
と言われる様になって来ました。
自分の心が喜んでいるか。
今、イキイキと輝いているか。
究極、生きるとは幸せになること。
自分の人生の主人公は「自分自身」であるべきはず…。
と言う考え方です。
楽しいか、楽しくないか?
そう感じるのには、大きく分けて2つの方法があります。
それは、体験(経験)する事。
そして、表現する事。
インプットとアウトプット。
いろんな経験を通して喜びを知る事。体感する事。
自分自身の思いや、気持ち、アイデア、想像を表(おもて)に現す。
具現化する喜び。
どちらも大切です。
生きていれば、色々な出来事に遭遇し、体験します。
楽しい事ばかりでは、有りません。
それをどう捉えるかは、その人次第です。
突き詰めれば、「体験」する為に、人は生きているのかも知れません。
体験して得る何かのために。
生きる「目的」は、体験する事…。
では、表現する事は?
続きは次回に。
前回の続きです。
何度か寄席に足を運んでいると、
結構同じ「演目」にぶつかることが有ります。
同日、出演者同志が被る…。何てことはさすがに有りませんが、
昨晩、新宿で聞いたお話しを次の朝、また上野で…。
これはデジャヴュなのか?
そんな訳は有りません。
演者が変われば、同じお話しでも、
まるで違った印象になります。
まずは、話の取っ掛かり「まくら」。
どんな内容のものを持って来るのか?
「掴み」はOKなのか?
話家さんの個性と力量が如実に表れます。
それと登場人物の設定、舞台となる土地や場所の
説明の仕方も各々、特徴があります。
あと、話家さんによって声の張り方や、
高低、口調なんかも十人十色。
表情、しぐさ、間の取り方も各人各様です。
なんと最後の「落ち」までが、まちまち。(ウソです。)
師匠から教わった「古典」としてのお話しは同じ一つのもの。
でも、「演目」として高座で演じられるのは、
その「演者」の数だけ存在しています。
その「違い」を体感することも楽しみの一つと言えます。
その違いを個性というのか、「味」と呼ぶべきか?
まあ、「味」が出るにはもう少しの熟成期間が必要かもしれませんが…。
同じお話しでも、表現方法はさまざまです。
病気も同じことです。
身体の状態の感じ方は、人それぞれ。
また、症状の訴え方も各人各様です。
何をストレスと感じるのか?
また、痛みと感じるのか?
その患者さんの身体が訴えかける「症状」という
お話しの主題「演目」は何なのか?
その方の背景に在る生活環境や人間関係、
その他諸々の条件も踏まえながら、
その「それぞれの表現」に謙虚に耳を傾ける必要性を痛感する…
今日この頃です。