-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年4月 日 月 火 水 木 金 土 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
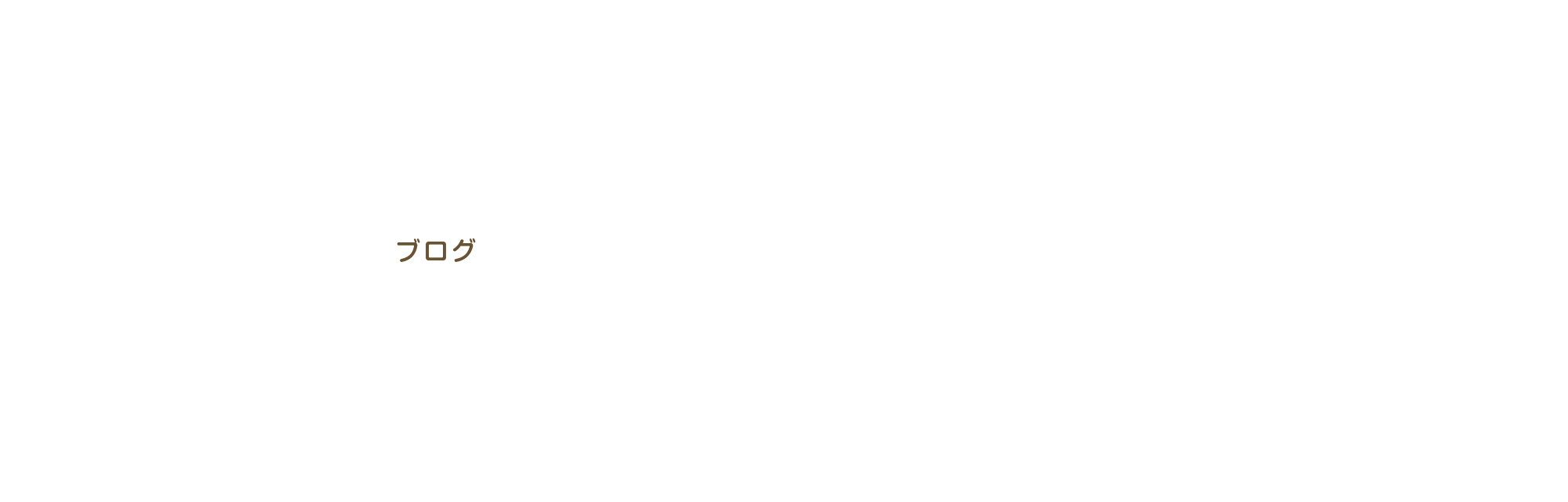
阪神間でも、前回の台風11号の接近以降、
お盆休みの間も大量の雨が降り、
各地で甚大な被害が出ています。
患者さんの中にも、天の橋立への旅行の帰り、
浸水被害の為にJRが不通で立ち往生されたり、
自宅の真ん前の電柱に落雷があり、
数時間停電を余儀なくされたり等々あったようです。
芦屋でも、奥池から有馬温泉に向かうバスが、
土砂崩れの為に不通となっています。
どうやらトンネル部分が崩れたようで、
復旧には年内一杯掛かる見通しのようです。
六甲山でも数カ所、
道路が通行止めや片側通行になっている箇所があります。
登山道も崩落して通れない場所があるようで、
こちらも復旧には時間がかかりそうです。
昨今の、局所的に大量の雨が集中して降る、
その降り方は異常です。
そろそろ地球規模での対策を
講じなければ行けない時期に来ているのかも知れません。
ただその「自然現象」である異常気象と、
河川の氾濫や土砂崩れなどの「自然?災害」は分けて考えるべきです。
それは、「お山の管理」と「治水」という
人為的な要因が関係するからです。
これまでも、山肌を削ったり木を伐採して開発を進めた結果、
今迄に無かった災害が発生している事は指摘されていました。
しかし、それとは逆に手付かずに放置されている里山が
土砂災害を増幅されている原因では?
とも言われ始めています。
それは、経済的な理由や人出不足などで、
間伐が十分に行われ無かった為に木が生い茂り、
日光が地面まで届かず、下草が育たないから。
だと言うのです。
その為に、地面の保水力が乏しく表面の土砂が剥がされて、
一気に斜面を下って行き易くなるんだそうです。
六甲山や摩耶山を歩いていると
土砂災害を防ぐための「砂防ダム」を至る所で目にします。
しかし、そんな砂防ダムを今回の台風では、
各地で、完全に塞いでしまったり、破壊したり、
またはその上を乗り越えて麓の人里まで土砂が流れこんでいます。
里に住む人間が、適正にお山の手入れをし、管理する。
これは中々に難しい問題です。
お盆休みも終わり、
今日18日から平常通り施術させて頂きます。
よろしくお願い致します。
今年は、今頃になって梅雨?というぐらい
雨の多い夏休みでしたね。
例年、お盆休みが過ぎるといろいろな事象に変化が見られます。
暑中御見舞いが、残暑御見舞いに。
海水浴も、「足を引っ張られるから」お終いに。
蝉の種類も鳴き声も変わり、ちらほらとトンボの姿も。
日差しも、雲の様子も、風の具合も
何となく違って感じられます。
というのは、数年前迄の話でしたが、
今年はどうでしょうか?
9月いや、10月過ぎまでダラダラと暑さが続くのか?
それともこのまま雨の多い、
結果的には冷夏と呼ばれるようなものになるのか?
何れにしても、体調管理の難しい
季節の移り変わりとなりそうな気配です。
それに備えて?
またこれからも皆様の心と身体の健康に
役立つであろう様々な情報を
ブログを通して発信して行きたいと考えています。
これからもよろしくお願い致します。
家族が毎日食事をしたり、眠ったりする同じスペースに、
仏壇や位牌といった祖先を祀る「祭壇」が在る。という所は、
世界的には、非常に珍しいようです。
日常の生活の中に、もう既に亡くなった方々が、居宅に存在する。
外国の方から見ると、「とても素晴らしいシステムだ。」と感じられるようです。
よく、一番身近なご先祖様は自分達の両親である。と言われたりします。
私達は、親や祖先からいろいろなものを受け継いで生きています。
苗字や、家や土地や財産。
仕事であったり、家柄や身分だったり。
長男、養子、嫁ぎ先。
事情はさまざまです。
でも、誰でもが確実に受け継いでいるものが有ります。
それは、DNA、遺伝子です。
先人が、生きてきた証し。
記憶としての情報が、
全ての人の肉体に脈々と流れています。
そういった意味では、
自分自身の肉体が最も身近なご先祖様。
と言えなくは無いと思います。
自分自身の身体の発する「声」に耳を傾けること。
自分自身の身体を大切に生きること。
それが、最も身近な先祖供養に繋がるのでは…。
くれぐれも「御身大切に。」
元来、仏教の教えで「先祖供養」を
説いているくだりは、ありません。
勿論、お釈迦様が仏壇や位牌について説法を為れた。
という記録は残されていません。
仏教が、インドから大陸を通り
中国、韓国に伝来した際に「儒教」の影響を受け、
先人を大切にする。という思想が加わりました。
それが、海を渡って渡来し
元々、日本にあった自然信仰や「氏神信仰」などと融合して
長い年月の間に現在の先祖供養という形に為ったと言われています。
(諸説あるようですが。)
氏神様と言えば、
「引っ越しをして来たら、近くの氏神様にご挨拶に出向いた方が良い。」
と言われるように、その地域を守護する神様(神社)と認識されています。
しかし、その成り立ちは読んで字の如く、
それぞれの「氏の神様」という意味が有ります。
「蘇我氏(そがうじ)」、「物部氏(もののべうじ)」のように
それぞれの一族を祀る社(やしろ)を
氏神様(神社)と呼ばれていました。
その一族を祀る社は、
「鎮守の森」と言われるように、
人々の住む「里」に近い「山」へと向かう森に鎮守していました。
元々、日本では「八百万の神(やおよろずのかみ)」と呼ばれるように、
岩や木や、山や滝といった自然の造詣物にも
「神」が宿るといった自然崇拝の信仰がありました。
ですから、亡くなった方々も「山」や自然に帰る。
と考えられていました。
山から来て山へと帰る。
それも、自分達の住む「里」から繋がっている「森」へと。
亡くなった方々が、身近で直ぐ傍(そば)に居て、
見守ってくれている。
そんな感覚を日本人は、自然と身につけています。
そんな感覚が、仏壇や位牌といった
「もの」に繋がっていったのでは?と考えられます。
続きます。
「少女時代」では、ありません。
「少年時代」です。
ある音楽番組で、「夏と言えば」だったか「夏に聴きたい曲は?」だったか、
どちらかで視聴者が1位に選んだ楽曲が、
井上陽水の「少年時代」でした。
私自身、好きな曲なので納得でしたが、
番組自体は、若者の見るもの?だったのでちょっと意外な感じがしました。
子供達に聞いてみると、
プレステ2のゲーム「ぼくのなつやすみ」で流れてくるから、
直ぐにイメージ出来るんだそうです。
どちらにしても夏休みと言えば、
ランニングシャツに半ズボンで、頭には麦わら帽子。
網と虫カゴを持って、カブトムシや蝉取り。
川に行ったり、沢ガニを見つけたり。
‘ござ’の上で昼寝して、
軒先につるした風鈴の音を聞きながらスイカを食べて。
縁側でたらいで行水。
家の前に打ち水をして、ついでに朝顔にも。
暗くなってくると、お墓で肝試しをしたり、
豚の蚊取り線香に火を着けて、
庭先で線香花火やネズミ花火をしたり。
夜になると、蚊帳が吊られた畳の間で
おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に眠りに着く。
懐かしい、幸せな記憶が現実にそこにはありました。
最近の子供達(大人も含めて)は、
ゲームや歌の中で擬似体験するしか、味わうことが出来ない…。
何だか寂しくなってきます。
多分、今はもっと楽しくて面白いことが一杯有るんだとは思うのですが…。
何れにしても、明日13日からはお盆です。
お墓参りに帰省される方もいらっしゃると思います。
杏林堂鍼灸整骨院でも
13日(水)〜17日(日)までお盆休むを取らせて頂きます。
お休みの間、ご迷惑をお掛け致しますが、
暑気あたりや熱中症などに十分留意されてお過ごし下さい。
久しぶりに大きな台風が兵庫県を通過しました。
毎年毎回、台風情報で凄いのが「来るぞ、来るぞ。」と脅かされながらの肩すかし?
が続いていたので、少々油断していました。
何の備えもしていなかったなぁ。とちょっと反省しています。
でも、本当にこの阪神間は災害などの少ない良い場所だとつくづく思います。
(阪神大震災を除いては…。)
このところの大雨で、停電や浸水、
土砂災害など各地で被害が出ています。
被害に遭われました皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
夏休みに入ってお盆前のこの時期に
これだけ雨が続くことは、例年では考えられません。
温暖化の影響なのか、海水温の上昇により、
台風がより強大となってゆっくりゆっくり進む為に、
その被害がより深刻なものと為ってしまっています。
まるで地球全体が「湿熱」という症状に罹患してしまったようです。
人間ならば、さしずめ「脾胃」を整えて、
「腎」で水分代謝のバランスを調整するのですが、
地球全体ではどうすれば良いのでしょか?
人間の場合は、熱と水分の排出法(出入り)は、2つ有ります。
それは、肺と大腸(小腸)です。
つまり、「呼吸」と「消化」(排便、(排尿))です。
地球自身も呼吸し、地球上で起こった事柄を消化(浄化)しています。
でも、近年ではその浄化能力をはるかに凌ぐ
「湿熱」が排出されているのかもしれません。
まず、その量自体を制限する必要が有ります。
その上で、水分調整。人間も地球も2/3が水分です。
多すぎても、少なすぎても良くありません。
では、海水量が増え過ぎない為には?
それは陸地の保全に掛っています。
陸地の保全には、何よりも森林の保全が重要です。
地球全体の呼吸という問題も含めて、
山や森林の大切さというものをもう一度見直す必要性があると思います。
地球の健康の為に私達が出来ることは、
まだまだ沢山あると思います。
何せ、地球の健康あっての私達人間の健康ですから。
蝶形骨という骨は中々に個性的で、面白い骨でもあります。
他には無い複雑な形状をしている上に、
頭蓋の中央でくさびのように頭蓋全体をまとめる働きも担っています。
その為に、調整もやっかいで
蝶形骨だけを単独で動かす事は不可能です。
また、蝶形骨は他の頭蓋骨の例に洩れず、
軽量化の為に?含気(エアーイン)状態で、
いわゆる軽石のようにスカスカです。
なおかつ、脳神経などのいろいろな神経が通る
小さな孔(あな)が空いています。
その為、強い刺激での調整は禁忌です。
よく小顔矯正などで、こめかみ辺りをグリグリしたり、
強く圧迫したりする映像をTV等で見かけたりしますが、
あれなどはちょっと考えものです。
痛みが残るだけで無く、めまいや吐き気、頭重などの
自律神経症状を発症させる可能性もあります。
前回の「耳ひっぱり」も直接、蝶形骨を触ってする調整法では無い為、
負担が少ないと思い、紹介させて頂きました。
また、蝶形骨のズレや歪みは、
身体のいろいろな部分の不具合が、
結果的に頭蓋骨のひずみと為って表れたものです。
それ故、蝶形骨を調整する為には
まず身体全体のバランスを整える必要があります。
以上を踏まえた上で、
蝶形骨の調整の概要をキーワードで記します。
⑴手首、足首、がん首
⑵尾骨から皿回し
⑶呼吸を合わせる
何がなんだか、よく分からない事と思います。
その詳細については、また日を改めて…。
「耳をひっぱれば疲れが取れる。
それどころイライラや不眠などのストレス症状も軽減する。」
そう提唱されているのが、
「1日1分であらゆる疲れがとれる耳ひっぱり」(飛鳥新社)の
著書藤本靖氏です。
アメリカ発祥の「ロルフィング」という
ボディーワークの施術者としても知られています。
その著書の中で蝶形骨の調整法として書かれているのが、
「耳ひっぱり」です。
藤本氏の論によると、蝶形骨は頭の真ん中にある骨で、
両側の「側頭骨」という骨に挟まれていて、
その側頭骨にくっついている耳をじんわり引っ張ると、
側頭骨と蝶形骨に「あそび」が出来て、
蝶形骨のゆがみが取れるというものです。
ひっぱり方には、藤本式「みひっぱりの基本フォーム」というのがあって、
まず姿勢は、
①背筋を伸ばす
②軽く呼吸をする(自然な呼吸)
③遠くを見るイメージで、視線は真っ直ぐに
そして、両手で左右それぞれの耳をつまんで、
①中指を耳のくぼみの中に入れ、
親指で耳の後ろ側の付け根をつまむ
②真横では無く「斜め後ろ」に
2〜3mmじんわりひっぱり10秒間キープする。
というものです。
※治療というのでは無く、簡単なエクササイズとして
誰にでも出来るテクニックです。
本ではその他の応用編なども記載されています。
ご興味のある方は、一読してみて下さい。
実際の施術の考え方…については、また次回から。
「蝶形骨」は頭蓋の多くの骨と接合し、
脳を支える頭蓋内の膜、
それに12対ある脳神経(視神経、三叉神経、副神経など)の多くと
直接、間接的にかかわり、
また内分泌系(ホルモンバランス)を司る
「脳下垂体」の受け皿(トルコ鞍)でもあります。
また、生命活動維持に重要な役割を果たしている
自律神経機能や体温、血圧、睡眠、歩行反射、
水分、食欲その他の調整機能を司っている
間脳、視床下部を含めた「視床」ともかかわりが有ります。
その為、蝶形骨の歪みは、
硬膜、脳脊髄液の循環、脳神経、内分泌系、自律神経系、
脳幹の働きに少なからず影響を及ぼす可能性が有ります。
そしてそれとは別に、
蝶形骨についている筋膜は、
ラップのように気管、食道、心臓を包み込みながら
身体の中心にある「横隔膜」まで繋がっています。
その為、深い呼吸にも関係し、
また横隔膜に接する腹腔内の各臓器にも
影響を及ぼすことが考えられます。
また、蝶形骨は顔面の中心、
目の奥にある大きな骨ですから、
顔や目のゆがみ、
鼻の症状(副鼻腔)等にも関連してきます。
身体の各所に間接、直接的に
さまざまな影響を与える蝶形骨ですが、
前回書いたように外側から全体を直接触れることが出来ません。
ではどうやって調整すれば良いのでしょうか?
続きます。
頭蓋骨の1つに、「蝶形骨」という骨が有ります。
頭蓋底の中央部に位置し、
その中央に脳の受け皿の役割をしている「体」と、
それから出る左右各一対の「大翼」、「小翼」及び「翼状突起」から成り、
ちょうど蝶が羽を広げた形に似ていることから、
この名前が付けられました。
そしてこの蝶形骨は、ほとんどの頭蓋骨と接合し、
中央部で楔(くさび)の様な役割を果たしています。
その為に、さまざまな理由で頭蓋にストレスが加わると
中心に位置する「蝶形骨」は、骨自体が圧縮されたり、
後頭骨との関節部分(蝶形後頭底結合)を支点として、
傾いたり、捻じれたり、ずれたりすることが有ります。
医学的には、成人の頭蓋骨は動かないと為れていますが、
実際はそうでは有りません。
蝶形骨という骨自体は、頭蓋内に在り、
全体を直接外側から触れることは出来ません。
しかし唯一、大翼の一部が触れる場所が有ります。
それが、目の外側の上、いわゆる「こめかみ」の部分です。
こめかみに人差し指をそっと当てて、
この大きな骨の「動き」を感じてみて下さい。
左右への膨張、収縮はかなり小さなものですが、
上下(前後?)に何と無く動いているのを実感出来ます。
呼吸に合わせてロールしているようです。
と言うよりも、この「くさび」のような骨そのものが静かに、
しかし休むこと無く、「呼吸」しているかの如き
「息吹」のように僅かずつ動いています。
理想的な蝶形骨は、左右、前後、上下方向に柔軟で、
ちょうど「脳下垂体」という赤ちゃんを乗せた
「ゆりかご」のような働きをしています。
その「ゆりかご」の動きが悪くなったら?
続きます。