-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年4月 日 月 火 水 木 金 土 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
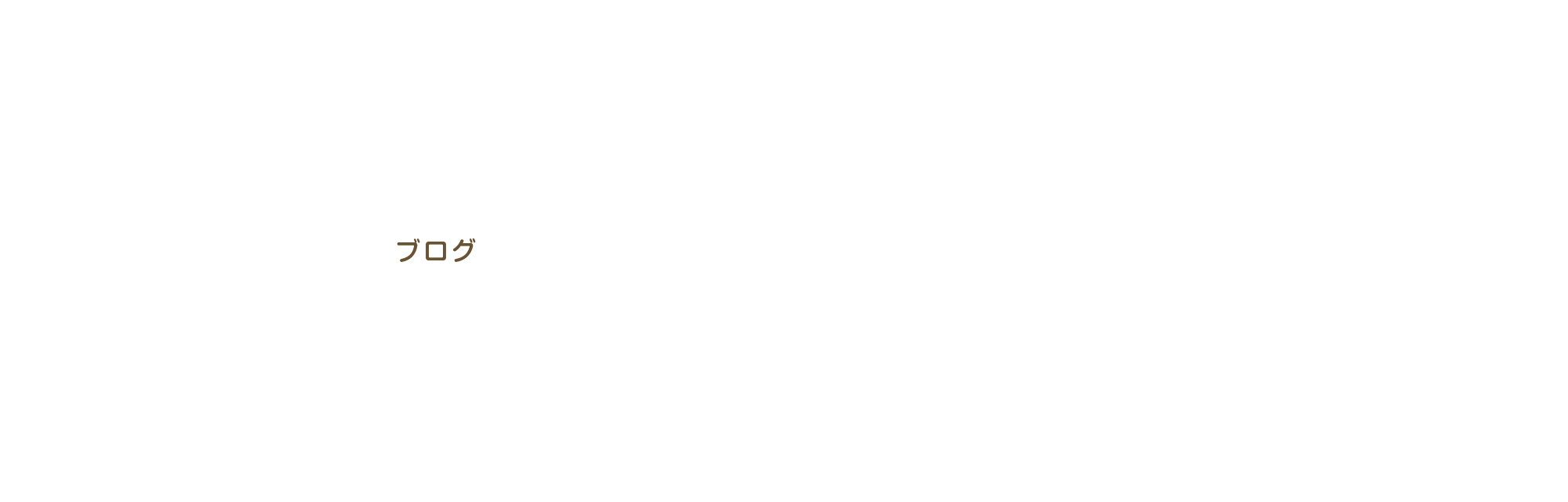
見えないものが見える。
そこに無い存在を感じる。
何かが聞こえる。
こういった現象はある種、
選ばれた人だけの特別な能力なのでしょうか?
それとも、幻覚、幻聴といった類いのものでしょうか?
あるいは、単なる思い込みや勘違いかも?
ある意味、どれも間違いではありません。
よく、閃きや直感や心の声、
前述のような能力なんかを「第6感」と呼んだりします。
5感を超越した感覚、
普通では説明のつかない不思議な出来事…。
のように思われますが、
ほとんどの場合、そんな不思議なものでも無く、
大抵は説明がつきます。
見えたり、聞こえたり、感じたり、ふと浮かんだり。
これら全てが、5感を通じての生体反応です。
現実には存在しないものを見る。
これは、脳の錯覚が引き起こす現象です。
私たちには見えないけれど、
本当は実際に存在しているものを、
ありありと目にしているというのなら、
それは普通に視覚を通した脳の正常な反応です。
幻覚であれ、何であれ、
全てが「肉体」を通じて起こる生体反応なのです。
風鈴の音を聞いて、実際には吹いていない風を感じる。
その場所に居ないのに、情景がありありと浮かぶ(見える)…。
エネルギー(気)感覚なども同じです。
何となく温かい感じがする。
逆に冷たく感じる。ピリピリする。嫌な感じがする。
重量感が有る。大きい、小さい。
丸い感じ、ゴツゴツした感じ、尖った感じ。
どれも、実際に目に見える「かたち」として
存在するわけではありません。
でも、「何となく」ですが感じます。
これこそが、記憶と情動と5感が結びついて起こる
脳の錯覚であり、それを利用して行われる
情報の書き換えと言えます。
そして、これらの感覚を開発する、
或いはアップさせる方法(可能性としての)が…。
それは次回に。
よく人間の意識は氷山に例えられます。
普段、私達が意識している部分を「顕在意識」と言い、
ほんのちょっとだけ海の上に出ている部分を指します。
そして目にすることが出来ない海中に沈んでいる部分、
つまり意識の大部分を占めるのが、「潜在意識」=無意識です。
表層に表れるている意識は、社会的文化的な欲求、
つまり「より人間として」「より自分らしく」といった願望。
深層にある無意識は、ずばり「生存の欲求」です。
さらに、この無意識の部分は、
個人的無意識と更に深奥に広がる
集合的無意識によって構成されています。
さしずめ、個人的無意識を「細胞」の意識、
集合的無意識を「種(しゅ)」の意識と呼ぶことが出来るかと思います。
そして、その無意識の最大の目的は
「安全、安定、安心」を得ることです。
生命維持(種の保存)にとって一番避けるべきは、「変化」です。
無意識それ自体には、夢も希望も、
また善悪も損得もありません。
ただ望むことは、現状維持=変わらないこと。
それが1番安全なのです。
「自分らしく生きる」ことを意識は望み、
「安全に生きのびる」ことを無意識は求め、
「ありのまま」に生きたいとつぶやく意識に、
「今のまま」が一番よ!と無意識はささやきます。
「生命を維持すること。」
この根源的な欲求は非常に強大です。
「安全、安定、安心」を脅かす「変化」に対しては、
全力で阻止しようとします。
(いや、無意識にとって一番の脅威は「変化そのもの」よりも、
変化に対する「恐れ」と、
変化へと誘う(いざなう)存在への「疑い」なのですが…。)
それこそが、潜在意識にアプローチする事を
困難にしている理由です。
では、どうすれば良いのでしょうか?
その方法が、恐れや疑いといった
「記憶」と「情動」が結びついたものが
「五感」を刺激して生ずる、
脳の「錯覚」を利用して「情報の書き換え」を行う…。
というものです。
※具体的なことは、さまざまな事象と共に
また改めて紹介して行きたいと思います。
次回は、ある種の能力開発について…です。
お金持ちになりたい。
素敵な結婚相手とめぐり合いたい。
ダイエットして綺麗になりたい。
いろいろな願望があるにも関わらず、
現実はなかなか思うように行きません。
それは、貴方の「潜在意識」が邪魔をしているからです…。?
願望達成や成功法則などの「自己啓発」関連の書籍等では、
この潜在意識という言葉を必ず目にします。
「希望を実現する為に潜在意識にアプローチしましょう。」
その為の方法もいろいろと紹介されています。
瞑想法や、睡眠法。紙に書いたり、何度も声に出したり。
でも、いろいろとややこしそうです。
恋愛願望を口にしても、それが叶わないのは、
潜在意識では「それ」を望んでいないからです。とか、
○○がしたい。○○が欲しい。
それは結局、現状○○を手にしていない、持っていないことを
逆に、強く意識させているだけです。とか、
○○にならない様に、などの否定語は駄目です。とか、
じゃあ、一体どうすりゃ良いんでしょう?
先ずは、「潜在意識」をちゃんと知る必要があります。
潜在意識は、顕在意識に対して意識に上がらない領域、
「無意識」とも言い換えられます。
では、その無意識とは意識の無い、
何も感じていない状態を指すのでしょうか。
そうではありません。
それは、最も深層の部分、
いわゆる原始的な意識とも言えます。
つまり、「生きる」こと。
この肉体を維持し、次に繋げる。
種の意識、細胞の意識とも言えます。
続きます。
8/28日、理研の利根川進博士らの研究チームが
遺伝子操作したマウスを使い、
「嫌な記憶」を「楽しい記憶」へと、
情報を書き換える実験に成功した。
という報道がありました。
人間やマウスの脳では、
「海馬」と呼ばれる部分が「出来事」を記憶し、
それが快か不快だったかは、
「扁とう体」に記憶されると考えられています。
利根川博士らの研究では、
雄のマウスを小部屋に入れて、電気ショックを与え、
海馬の特定の神経細胞群を活性化させて
「小部屋の中は怖い。」と記憶させます。
そして再度、この細胞群を「光」で活性化させると、
小部屋の外でも、思い出して恐怖で身をすくめる反応を示しました。
ところが、同じ神経細胞群に光を照射しながら
雌のマウスと一緒に過ごさせると、
今度は「楽しい経験」として記憶され、
小部屋に入れても恐怖反応を示さなくなったというのです。
「記憶を書き換える」と言っても
過去の出来事そのものが変えられるわけではありません。
その出来事に対する「反応」に変化が生ずる…という事です。
例えば、怒られてばかりで「辞めてやる。」と思っていたクラブ活動も、
いざ卒業となると全てが良い思い出に。
失恋のショックで泣き明かした日々も、
幸せな結婚生活を送っている今では、
意識にすら上がることがありません。
また、無愛想で変わり者のオジさんの態度が、
大学教授だと知ったとたんに、
何だか威厳に満ち溢れたものに見えて来ました。
どれも、海馬から扁桃体へ繋がる神経細胞群に「光」刺激を与える。
つまり、情報の書き換えが行われているわけです。
今回の研究結果はうつ病などの心理療法に、
将来応用出来るだろう。との事でしたが、
それだけで無く「痛み」や「機能障害」などなど、
様々な疾患にも有用であると考えられます。
また、情報の書き換えは治療行為にとどまらず、
「潜在意識」と呼ばれる領域にも…。
そのお話は、次回に。
・実際には無いものを感覚として捉える。
そして、それが現実に生体反応として表れる。
・実際に存在していて、
なおかつ脳が認知しているにもかかわらず、
意識に上がらない。
「風鈴」と「瞑想」の2つの実験は、
内容は違えど、どちらも同じことを示唆しています。
それは、「体性感覚(5感)」に「記憶」と「情動」が結びつくと、
生体反応に変化を及ぼす可能性がある。ということです。
・風鈴の音を聞いて(聴覚)、
涼しげで心地よい情景が浮かび(記憶、情動、視覚)、
風を感じて(触覚)、体温が下がる。(体温中枢)
・瞑想中にランダムな刺激を受けて(聴覚、視覚、触覚、嗅覚)、
脳波が触れるのは、正常な生体反応です。
しかし、刺激が無くなった後も続く反応は、
不快感やストレスなどの記憶と情動が5感と結びついて、
起きたものと言えます。
記憶と情動が結びついたもの。
つまり、いわゆる「こだわり」や「思いこみ」といった類いのものから、
「恐れ」、「怒り」、「悲しみ」、「疑い」や「喜び」、「愛情」
などなどが5感に働きかけて
「脳の勘違い」、「錯覚」といったものを引き起こします。
それが、良い反応として表れる場合もありますし、
逆の場合もあります。
病気や精神的な疾患などの
身体反応として表れる場合もあり得ます。
そんな場合の対処法(治療)は、
脳の勘違い、錯覚を逆に利用するのです。
その方法は、
「記憶の差し替え」、「情報の書き換え」と呼ばれます。
錯覚と情報の書き換えについては、
また次回説明します。
「心頭滅却すれば火もまた涼し。」
何事も気持ちしだい。
集中してことを行えば、熱さも痛みも何も気にならない。
スポーツでも、その一球に集中している時は、
まわりの雑音が聞こえなくなり、
何かに熱中している時は時間も忘れ、
格闘技では、試合中の記憶さえ無い時もあります。
そんな集中して「気」を高めることが上手な人と、
逆に気が散漫なタイプの人がいます。
その差はいったい、どんな所からくるのでしょうか?
これもかなり以前に、
あるTV番組で変わった実験が行われていました。
それは、集中力が高いタイプの方と、
そうで無いどちらかと言うと落ち着きの無い方?の
2組数名を一室に集めて、静かに目をつぶって瞑想してもらうのです。
そしてある程度、落ち着いた時点でいろいろな刺激、
例えば、「子供達の話し声。」や「大きな物音。」
「光刺激。」「触れる。」「匂い。」などなどをランダムに与えて、
その際の反応と「脳波」を観察、記録するというものでした。
実験前の予想では、集中している組は、
「脳波の変化が少ない」のでは?と考えられていたのですが、
結果は意外なものでした。
落ち着きの無いグループは、
刺激によって変化に多少の差があったのですが、
集中組は刺激に関わらず、
その振れ幅がどれも無い組よりも大きいのです。
つまり、刺激(変化)に対して「敏感」なのです。
ただ、2組のその後の変化には、大きな違いがありました。
落ち着きの無いグループは、
一旦脳波が乱れると、なかなか収まりません。
しかし、集中組の方は大きく振れて、
すぐにまた安定した波形に戻るのでした。
これは、集中していれば「何も感じない。」のでは無くて、
かえって敏感になっているけれども
すぐにその影響下から離れることが出来る。
逆に無い組は、外部への反応も内部での対応も
散漫でコントロールが出来にくい状態だと言えます。
これは、1つには「情動」が関係していると思われます。
この実験結果も非常に興味深いもので、
「風鈴」の場合と同様にさまざまな分野に応用することが可能です。
それは…。
また、続きます。
軒先に吊るされた「風鈴」の涼しげな音色。
夏の風物詩です。
と言いたいところですが、最近はちょっと事情が違うようです。
一日中、クーラーを作動させている為に、
窓はずっと閉めっぱなしで、
風鈴そのものを目にする機会すら少なくなっています。
そんな風鈴に関して、
以前あるTV番組で興味深い実験がありました。
それは、人は「風鈴の音を聞いて本当に涼しくなるのか?」
というものでした。
被験者は事前に何の説明も受けずにある一定の室温の中、
目隠しをされた状態で風鈴の音を聞かされます。
そして、サーモスタットで体表面の温度の変化を観察します。
その結果は…。
涼しく「感じる」だけで無く、
実際にほとんどの方の体温が低下しました。
風鈴が鳴っている状態=風がある→涼しい。
という条件反射みたいなものです。
人によっては実際に「頬に風を感じた。」方もあります。
部屋の中は無風状態なのに…。
「風景が目に浮かぶ」人もいました。
考えてみれば、これは凄いことです。
ほとんどの方が…ですが、
体温に変化が無かった人もいました。
それは、風鈴をよく知らない?若者や子供達でした。
ならば、と言うわけで外国の方に同様の実験をしたら、
案の定?1人も変化が有りませんでした。
それどころか、涼しげなはずの風鈴の音色を、
ただ単なるノイズと感じて却って、
若干体温が上がる人さえいました。
番組的には、四季のある日本人の繊細な感覚や情緒という点に
スポットが当てられていましたが、
それだけでは無いと思います。
この実験結果には、
治療やある種の能力開発に応用出来るものが内包されている、
と言えます。
それは…。
続きます。
「自宅のリビングでくつろいでいる様な感じ。」の治療所にしたい…。
それが始まりでした。
ご近所で懇意にさせて頂いていた設計士さんに相談したところ、
「こんなのが、有りますよ。」と言って持って来て下さいました。
それが、「檜の間伐材」と「杉の腰板」でした。
節(ふし)の無い一本の床柱を育てる為に間引きされた、
その他大勢の節だらけの檜達。
それが、檜の間伐材です。
ある程度の硬さがあるので、製材されて床材となります。
そして、壁には杉の間伐材を。
真っ白い壁紙は、
いかにも「病院」という感じで冷たい雰囲気がするし、
かと言って壁一面が、杉板だとログハウスか、民芸酒場に間違われるし…。
というわけで、腰までの高さにして「杉の腰板」に。
檜の床材を貼る前には、竹炭の粉末を一面に敷き詰めてあります。
そして壁や天井には、杉板以外の部分に
ノンホルムアルデヒドのクロスを貼っています。
無垢材のままでも良かったのですが、
防腐や傷のことを考慮して表面に「柿渋」を塗っています。
とにかく自然素材にこだわって内装をして貰いました。
でも、全ての材がいわゆる商品価値の無い
「間伐材」を使用しているので、
新建材のフローリングよりも却って安く上がりました。
何よりも、とても落ち着くし居心地が良いです。
「節くれだらけ」なのが、気にならなければ
(これはこれで、却って「味」がある。と思うのですが…)
とてもお買い得な「商品」だと思います。
最近では、オガクズやチップを使った「バイオ燃料」など
間伐材の利用価値は少しずつ増しています。
しかし、まだまだ「産業」として成り立つ程には至っていません。
農業にしろ林業にしろ、
それを担う人達の生活が充分に成り立っている事。
翻ってそれが、私達の安全や安心、
また国土の保全に繋がっているのでは、と思います。
というわけで?「檜の間伐材と杉の腰板。」でした。
お山の管理の問題は、「災害」だけでは無く、
私達の「健康」にも影響を及ぼしています。
日本の森林の4割を占める人工林では、
一定面積内に非常に多くの本数の苗木を植えて、
数年ごとに間伐を繰り返し、木の成長にあわせてその都度、
適正本数を保つように調整しています。
何故そんな事をするんでしょうか?
それは、林業を1つの「産業」として捉えれば理解出来ます。
杉や檜、松などの針葉樹は
密集して植える事で真っ直ぐに育ちます。
まばらに植えられた苗木は、
下の方が太く先端に行くに従って細くなります。
木としては健全な成長とも言えますが、
木材としての商品価値としては、
真っ直ぐな材の方が望ましいのです。
商品としての木を育てる為には、
先ず地ごしらえを行い、苗木を植え、
それから数年は下刈りという作業を続け、
10年を過ぎると枝打ちが必要となり、
これを30年近くの間に計5回。
そして、間伐です。
8〜10年頃から育ちの悪い木や、
育てようとする木の邪魔になる木を伐採し、
その後も5年おきに、10〜25%間引いて行きます。
そうして40~50年、或いは70年かけて主材となります。
膨大な作業、手間と費用と人手と年月をかけて育て上げた木。
それが…間伐材は勿論の事、主材ですら、
輸入材に圧されて原木市場で買い叩かれてしまうのが、
日本の林業の現状です。
その為に、植林された木材の手入れが侭ならなず
放置されてしまします。
日本国中、杉や檜だらけというわけです。
それが、花粉症が近年増加している原因の一端とも言えます。
アレルギー症状は、本人の体質改善や予防なども勿論、
大切な事柄では有ります。
しかし、それだけでは無く、環境問題や産業構造など、
国としての施策も非常に重要な課題でもある。と言えます。
以前のブログでも書きましたが、
再来年「山の日」を制定するのにあたり、
休みを増やすばっかりじゃ無くて、
もう少し「お山の管理」という問題も考えて欲しいと願います。
広島市で発生した土砂災害。
本当に何と言って良いのか。
ニュースの映像を見て、言葉を失いました。
広島市安佐北区に勉強会などで、
大変お世話になっている先生がいらっしゃるので、
心配していたのですが、
昨晩、「何事も無く、無事です。」という内容の新着ブログがアップされて
ホッと胸をなで下ろしました。
ほんのちょっとの所で、被害の状況には雲泥の差があったようです。
今回の災害も、本当に他人事では有りません。
私達の住む芦屋や神戸でも、
同じような地形の所は、たくさん見受けられます。
南北に海と山に囲まれた狭い土地に、
住宅がびっしりと建ち並ぶ街並み。
当然、山へ山へと開発の手は拡がって行きます。
芦屋川や高座川の上流の「こんな場所に」というところまで、
新しい大きな家やマンションが建っています。
今回のように、わずか3時間の間に8月の1ヶ月分の大量の雨が
狭い地域に集中的に降れば、
この辺りも果たして大丈夫なのでしょうか?
考えてしまいます。
改めて、最近芦屋市から送られて来た
「防災ハザードマップ」を確認してみました。
やはり、市内のかなりの地域が
土砂災害の危険地域や警戒地域に指定されています。
それだけでは無く、43号線より南の地域は、
殆どが「津波」浸水に注意が必要。となっています。
何も、むやみやたらに心配ばかりする必要は無いのですが、
もう1度改めて、自分達がどういう所に住んでいるのか
「防災マップ」で確認されては如何でしょうか。
避難場所や、そこへ向かう避難経路も
実際に歩いて見るのも、悪くは無いと思います。
芦屋市も、1人暮らしのご高齢の方が沢山いらっしゃいます。
小さいお子さんや、障害の在る方も含めて、
いざという時に直ぐに避難が出来る体制を
地域を挙げて日頃から考えていく必要性を
今回の災害で痛感為せられました。
家でも、家族と避難方法や連絡方法など、
話し合わなくては!と思います。